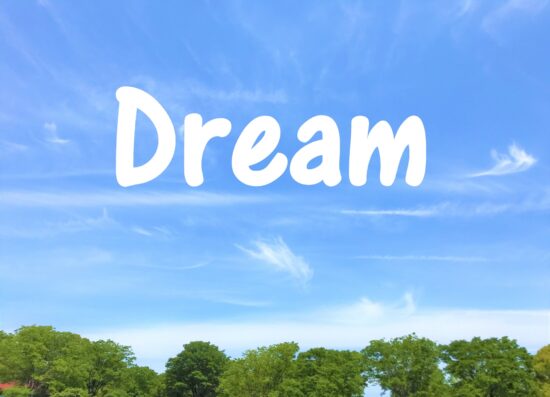
私達はよく、『信じる者は救われる』という言葉を引用して、
「いいから言われたとおりにやってごらんよ」的なことを促したりします。
当たり前に誰でもが使っていますが、この言葉はやっぱり宗教から来てるんですよね。
私達日本人は、外国の方からは不思議がられるほどに特定の宗教を持ちません。
というより、避けてさえいます。
そのくせ
クリスマスはキリスト教 どなたか亡くなったら仏教
新年を迎えると日本神道で神社へ 新築の家を建てるときも神道の神主さんを呼びます。
そして宗教心も無いくせに
『信じる者は救われる』
笑いたくもなりますが、
なぜここまで日本人に浸透しているのか
探ってみることにしました。
「信じる者は救われる」とは何か
あらためて、「信じる者は救われる」という言葉は、特定の宗教や信仰を持たない人々の間でも広く使われる、非常にポピュラーな表現です。私たちはこの言葉を、努力や信念を持ち続ければ、必ず良い結果に繋がるという、前向きなメッセージとして捉えがちです。
しかし、この言葉の背後には、深い宗教的・哲学的なルーツと、時代や文化によって変遷した意味が隠されているようです。
この言葉の元ネタは誰の言葉か
この言葉が最も直接的な形で用いられている元ネタは、キリスト教の聖書です。
特に新約聖書のマルコによる福音書やヨハネによる福音書に、イエス・キリストが弟子たちや病人を癒やす場面で、「あなたの信仰があなたを救った」といった類いの言葉を語る記述が数多く登場します。
これは、単に奇跡を信じるという受動的な態度だけでなく、「イエスという存在を信じ、その教えに従って生きることこそが、魂の永遠の救済に繋がる」という、キリスト教の根本的な教義を表しています。
英語での表現とその意味
この言葉に相当する代表的な英語表現は、「Believe and you shall be saved」や「Faith saves」などです。
英語圏でのこの言葉の解釈も、多くの場合、キリスト教的な文脈(信仰が罪からの救いをもたらす)が基本ですが、より日常的なレベルでは、「自信を持って行動すれば、成功する」という意味合いでも使われます。
聖書と仏教における解釈
| 宗教 | 「信じる」の対象と意味 | 「救い」の概念 |
|---|---|---|
| 聖書(キリスト教) | 神(イエス・キリスト):神の愛と教えを心から受け入れること。 | 罪からの解放、永遠の命:信仰によってのみ与えられる、魂の根本的な救済。 |
| 仏教(浄土真宗など) | 阿弥陀仏(阿弥陀如来):仏の誓願(本願)の力を疑いなく受け入れること。 | 迷いの世界からの解放(往生)、悟り:自力ではなく、仏の力によって極楽へ導かれる。 |
このように、両者とも「自己の力だけではどうにもならない問題を、より大きな存在の力によって解決する」という意味合いで「救い」を捉えています。
「信じる者は救われる」とは何を意味するのか
この言葉が現代の私たちに意味することは、大きく分けて以下の2つです。
- 自己効力感の創出:自分にはできる、という「信念」を持つことで、困難な状況でも諦めずに努力を続けられる。(難しい言葉でごめんなさい)
- 安心感の獲得:自分一人ではなく、何かに支えられている、という「信頼」を持つことで、精神的な安定と平穏を得られる。
この言葉が私たちに与える教訓
現代を生きる私たちにとって、この言葉は、不確実な未来や、努力が報われるか分からない状況において、行動を続けるための心理的なエンジンを提供してくれます。
例えば学校の試験のための勉強。試験の問題がわかっているわけではないので、どこまで掘り下げて勉強すればいいのか先が見えませんでしたよね。でも、「もう少し ここまでは」みたいに「自分はここまで頑張ったんだ」って自信を持てるまで勉強することで試験の結果が向上するであろうことを『信じる者は救われる』と、念仏のように唱えながら勉強した記憶があります。
社会人になっても、営業の実績が上がらないで悩んでいるとき、信じてお客さんを廻っていけば、必ず素晴らしいお客さんに出会えるはずだと、これも同じ気持ちですよね。
この考え方があったからこそ、頑張り続けられたという経験は、どなたもお持ちなのではないでしょうか?
「信じること」は、努力を継続するための「希望」であり、それは最終的に良い結果を生む可能性を高めるという教訓を与えてくれます。
信じる者が受ける救いの実例
イエスの教えに基づく救いの概念
聖書における「救い」は、病が治る、貧困から解放されるといった現世的なものだけでなく、「心の状態が根本的に変わる」ことに重点が置かれています。
信仰によって、人は不安や恐れから解放され、希望を持って生きる力を得ます。これこそが、宗教が提供する最大の「救い」の実例です。
引き寄せの法則との関係
近年流行している「引き寄せの法則」の考え方は、この「信じる力」を心理学的に解釈したものです。
- 信じる:自分が望む結果を強く信じ、それに意識を集中する。
- 結果:その信念に基づき、無意識のうちに行動や思考が変わり、結果的に望む状況を引き寄せる。
つまり、信じることで「救いの手」が差し伸べられるのではなく、信じることで自分自身の行動が変わるというメカニズムが、現代的な「救い」の実例と言えるでしょう。
信じることで得られる幸せと喜び
信仰や信念がもたらす最大の幸福は、「人生の意味と目的」を見いだせることです。
- 目的意識:目標を信じることで、日々の単調な作業にも意味と価値を見いだせる。
- 幸福感:目標に向かって努力している自分を肯定できるようになり、結果にかかわらず幸福感が高まる。
信念の強さがもたらす結果
スポーツ選手や起業家の成功譚は、信念の強さが物理的な結果をもたらすことを示しています。彼らは、「必ずできる」と信じ続けることで、並外れた練習量や困難な課題を乗り越えるエネルギーを生み出しているのです。
「信じる者は救われる」に関連する投資
「信じる者は救われる」アニメの紹介
「信じる者は救われる」というテーマは、アニメや物語でも頻繁に登場します。
例:「ワンピース」という作品では、主人公が仲間との絆や自分の力を信じ抜くことで、絶望的な状況を打破する様子が描かれています。これは、現代の日本人がこの言葉をどのように解釈し、行動の指針としているかを示す好例です。
この言葉をテーマにした人気のランキング
自己啓発書やビジネス書ランキングでは、「自分を信じる力」「成功の法則」といったテーマが常に上位を占めています。人々は、宗教的な救いだけでなく、世俗的な成功や幸福を信じる力によって得たいと願っていることがわかります。
信じることの力を実感した成功例
成功者の多くは、周囲が不可能だと笑った目標やアイデアを、誰よりも強く信じ抜いた人々です。彼らは、「信じる」という行為自体が、行動のエネルギーを生み出すということを実証しています。
信じることで人生が変わる理由
信頼と信念の重要性
人生を変えるのは、「信じる」という行為によって生み出される**「継続的な行動」**です。
- 信頼(Trust):他者や環境、あるいは自分を支える何かの力を信頼することで、不安を乗り越えて一歩踏み出せる。
- 信念(Belief):目標達成を確信することで、困難に直面しても挫折することなく、行動を続けられる。
行動が結果を生むプロセス
「信じる」と「救われる」の間には、必ず「行動」が存在します。
信じる → 希望を持つ → 不安を乗り越える → 行動を継続する → 結果(救い)を得る
救いは、ただ待っているだけでは訪れず、信じることによって生まれた行動の結果として得られるものなのです。
信じることによって、同じように行動しても、その動きに覇気を感じたり目が生き生きとしていたり、言葉に力が宿ったりします。その結果周りの人たちを巻き込んで、その人の思いを実現させていったりします。
自分自身の考えを疑っている人の言葉や目つきに力を感ずることはできませんものね。
「選択」と「行動」の関係性
人生の転機(前回の記事参照)において、人は様々な「選択」を迫られます。
「信じる」ことは、困難な道や不確実な選択であっても、それを正しいと確信し、突き進む勇気を与えてくれるのです。この確信に基づいた「行動」こそが、最終的に人生を変える結果を生み出します。
まとめと本当の意味の探求
読者への問いかけと未来への提案
「信じる者は救われる」という言葉の真の意味は、「何を信じるか」ではなく、「信じるという行為を通じて、あなたがどう行動するか」に集約されます。
あなたは今、何を信じていますか?
- 自分自身の可能性?
- 家族や友人の愛?
- あなたの努力が報われる未来?
その答えが、あなたの次の行動を決定づけます。
「信じること」が必要な理由
私たちは皆、人生で必ず困難や不安に直面します。そんな時、「信じること」は、私たちを暗闇から引き出し、希望へと導くための、最も強力で普遍的な心のツールとなります。
信じる者は救われるというメッセージの真理
「信じる者は救われる」というメッセージの真理は、救いが外部からもたらされるのを待つのではなく、信じる力によって自ら救いの道を作り出す、という主体的な生き方にあるということですよね。


コメント